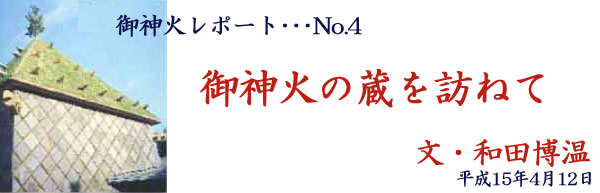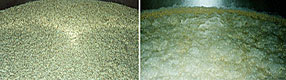竹芝を夜10時に出航したサルビア丸は、土曜日の早朝6時に岡田港に着岸した。 20年ぶり(いや、それ以上か)の伊豆大島である。念願かなって「御神火」の蔵、谷口酒造を見学させていただくのだ。杜氏でありながら「一円大王」の著者という作家の一面もお持ちの異才。その著書のカバーを飾る著者像は、南伸坊氏のイラストだ。写真ではない、イラストである。そう念を押しておきたいほど似ている。コインのように丸いふくよかなラインで描かれた谷口さん、実物もまさしくそのとおりのキャラクター。この丸い温厚なインターフェイスの底に、繊細で豪胆、強靭な意志と透徹した感性が潜んでいる。谷口さんとは、焼酎の会や神楽坂の焼酎バーでご一緒したことはあった。だがカウンターに座っている谷口さんから焼酎を造っている姿を思い浮かべるのは難しかった。
「そろそろ造りを終わります。麹作りは終わりましたし、いま仕込んでいるもろみを蒸留したらお仕舞いです」と城達也ばりの渋い声が受話器の向こうから朗朗と響いてきた。 「土曜日に蒸留しますが、どう?」 「行く!行きます!行かせてください!」 港の沖で停泊していたさるびあ丸は、夜明けとともに機関を始動。6時定刻に岡田港に入港した。うかつなことに小生はここを元町港と勘違いしていた。昨夜の二等船室はよっぱらいオヤジたちのイビキの交響でとても寝られたものではなかった。蔵まで歩いても30分はかからないだろうしちょっと仮眠してゆこうと思った。それが二つ目の間違いだった。船が着岸してまもなく元町港行きのバスが発車していたのだった。7時半のバスで元町港へ。そこでバスを乗り換えた。初老の運転手氏が発車時刻になるのを待っていた。 「ノマスに行きますか?」 「ノマシだよ。行くよ。10分はかからないな」とぶっきらぼうだが的確な返事。ほっとした。
8時をすこし過ぎたとき、一台の四輪駆動車が登場した。谷口さんご夫婦と愛犬テツくん(柴犬)の出勤である。奥様の香(かおり)さんはグラフィックデザイン畑の出身。この蔵の製品のグラフィックは奥様が担当されているのだろう、どれも秀逸である。 「テイスティングといっても蒸留直後の度数のつよい焼酎です。しっかりおなかを作ってくださいね」と、シラスがたっぷりはいった豆ご飯と薫り高いおみそ汁を用意してくださった。滋味に富んだじつに美味しい朝食をいただいた。 ごちそうさま、準備完了です!
モチヅキさんと小生は、杜氏に密着し、蒸留の全過程を、垂れてくる焼酎の色を、香を、味をみながら共有するという、まことに得難いそして幸せな経験をしているのだった。火をたき、冷却しつつ原酒を造っていく緊張の3時間。谷口さんの五感が原酒の最終形にむけて研ぎ澄まされてゆく。ハナ垂れ、中垂れ、そして末垂れと言葉にすればそうなることのそれぞれの過程と生まれる焼酎の香味の複雑さ、深さ。午前午後の二回の蒸留にすべて張り付いての作業が終わったのは午後3時半。 「きょう蒸留した焼酎は、おなじ白麹でもいつもとは型のちがうものを使ってみたんです。」 L型というその白麹、S型よりも香がたつ麹なのだそうだ。
雨の大島。御神火の蔵もやがて今期の活動を終える。酒を生む蔵から蒸気が立ち上る。火と水の修羅からひとの心を温める酒が産まれる。おひるにご案内いただいた、蔵の裏山、水源地ちかくの椿のトンネルに、一輪二輪真っ赤な残りの花が鮮やかに咲いていた。 焼酎は知恵と感性を注ぎ込んで造る。だが体力がなくては始まらない。蔵の中の作業は体を動かし手を動かさなくては何もカタチをなしてこない。筋肉の疲労も精神的な疲労も造りを続けるうちに、知らず重なり、厚みを増してくる。体をやすめ、気を散じて自分のなかに「空」を作ってください。次のチャレンジのため、さらに元気を生むために。谷口さん、奥様ありがとうございました。ハカセ、またお会いしましょう。 おわり。 |